道化の歴史
皆様は、道化といえば、ピエロやクラウンを思い浮かべるでしょう。
ピエロやクラウンという名の道化は、西欧で誕生しました。
その道化の歴史の変遷についての考察をしたいと思います。
また、日本でなじみの深いピエロと、道化の総称であるクラウンとの関わり合いについて
も考察しました。
ヨーロッパにおける道化の系譜
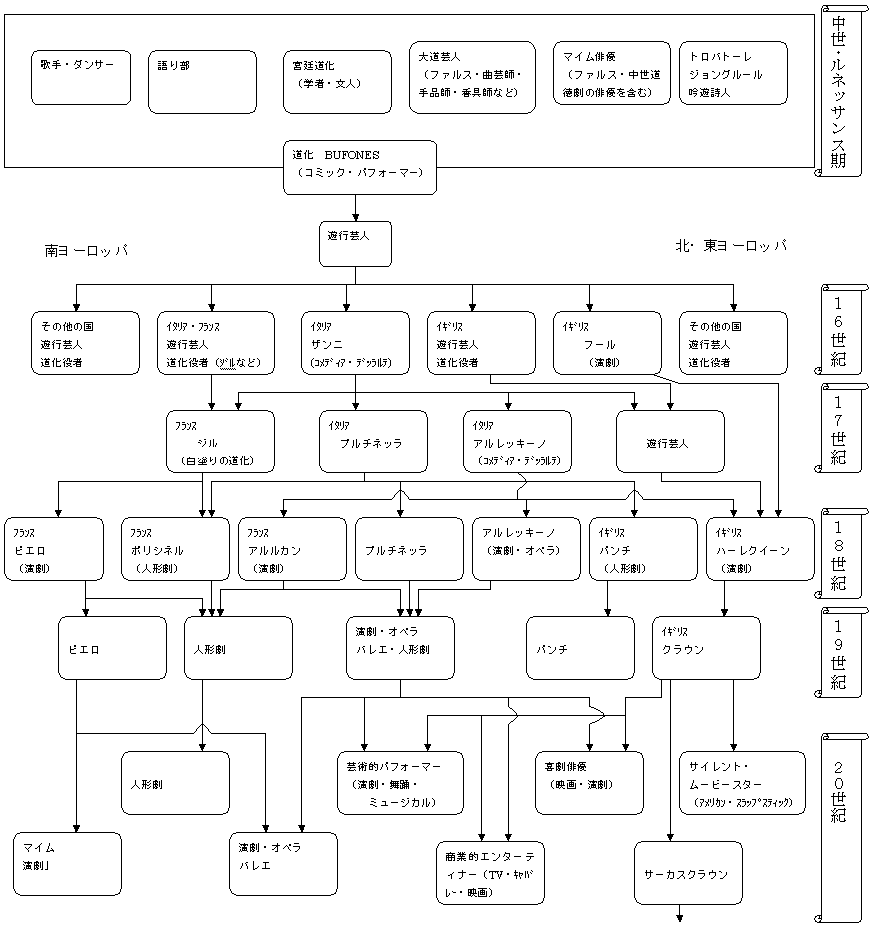
第1 道化の起源と中世の道化
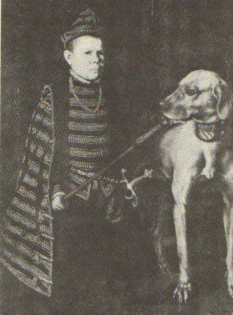 |
宮廷愚者
(ジェスター)
|
西欧に於いては古くから白痴、狂人、不愚者が宮廷や貴族の家などに置かれ、遇者(フール)
と呼ばれていた。この起源は明らかではないが、一つは魔よけとしての愚者が拳げられる。
もう一つは詩人、透視者としての愚者である。これら愚者は王や貴族に召抱えられ、宮廷愚者(ジェスター) (2)
と呼ばれた。 宮廷愚者は、貴族間で交換されたり、王の贈り物とされた。
ルネッサンスに於いては、愚者の芸が、本当に成功したときには、現代の映画スターの評価のよう
なものを得ることもあった。
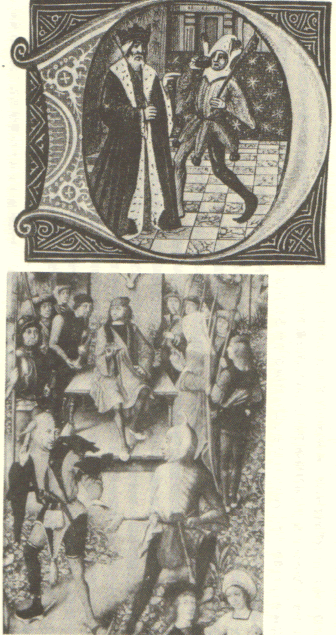 |
フール
(愚者)
|
この頃、彼らの中には、精神と肉体が、真に風変わりだけでなく、パロディー、物まね、即興の才
を持つものもいた。当時の王候貴族たちは、自分の愚者の賞賛を自分自身への賞賛と考え、愚考や
奇形の見本を所有する事に誇りを持っていた。
またこの頃の道化師は、機智に飛んだ言葉や面白い悪戯をすることにより、また貧しい人の味方
として、きわめて愉快なものとして皆に愛された。
16世紀に様々など受けが存在したが、後世に生き残ったのは、鋭い風刺の才を持った、騒々しく
挑発的な道化役者であり、おどけた所作や粗雑なふざけが、大衆受けのする道化の特質となった。
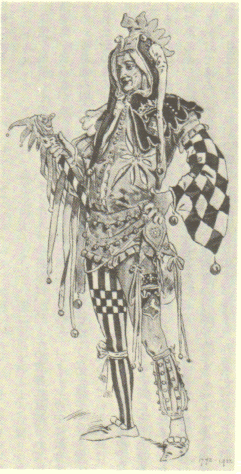 |
フール の 衣装
(シェクスピアお気に召すままのフール)
|
中世の道化の衣装は多少様子を変化させているが、鈴付きで先のとがった帽子と耳づきんの組み合った
被り物と、先のとがった靴、道化棒が多くの共通するものである。
また上着は、まだら模様であり、それが道化の公の標章のひとつであった。
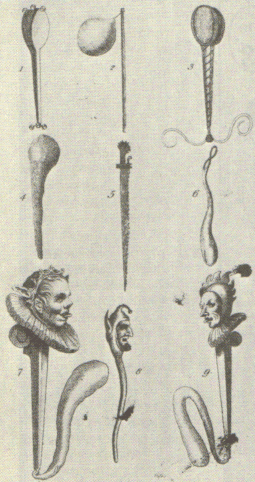 |
道化の棒 |
第2 放浪芸人に於ける道化
中世のヨーロッパには、旅回りの芸人が存在し、諸国を放浪し、多くのレパートリーで人々を楽しませた。
村に定住し、土地に縛り付けられた農民にとって、このような旅回りの芸人たちは、下界の出来事を知る為の
貴重な情報源であった。彼らは、社会的には、低い地位に置かれていたが、時には、王侯貴族の館に呼ばれ、
エンターティナーとしても奉仕した。かれらは、行く先々での多様な観衆の要求に答えるため即興の能力
を持っていたとされる。
 |
コメディア・デラルテの仮面 |
ヨーロッパの経済状態改善されるにつれ、彼らの社会的地位も多少向上したようだ。イギリスでは、自分の言葉を得た
ジャックプティングへと変身し、大道薬売りに雇われ、広場に集まる群衆を引き寄せる役目を持ち、祭りの広場で
盛んに活躍した。後にジャックプディングは、即興のショーや綱渡りの上で、おどけたアクロバット、ジグ舞曲
などを行い人気を得た。17,8世紀のイギリス、特に外界からのニュースが稀な田舎では、風刺新聞の売り子や
彼らの曲芸師が歓迎され、大きな成功を収めていた。また大道芸人たちは、風刺とおどけが上手く演技ができれば、
経済的に自立していくことができた。
またイギリスに於いて旅回り一座は、ロンドンの劇場で大ヒットした演劇をいち早く取り入れ、これを面白おかしく
上演した。これは茶番(ドロール)と呼ばれ、これによりイギリス演劇の名作は、国民に浸透していった。
この茶番で人気者だったのも、道化である.
第3 道化役者
 |
アレッキーノ |
現実社会に於いて宮廷愚者、宮廷道化師が存在し、活躍する頃、舞台に於いても道化役が出現し始める。
16世紀以降の道化役を活躍させたものにコンメディア・デッラルテという即興喜劇がある。「演劇の歴史」
によるとコメディア・デッラルテの要約は以下の通りである。1550年頃イタリアで生まれたコメディア・
デッラルテは旅回りの劇団によってヨーロッパ中の劇場、村や町、時には王宮で上演され、あらゆる階級の
この人々に笑いの種をまいたとされる。この劇における俳優の対話は筋は与えられていたが、全くの即興だった。
コンメディア・デッラルテの初期の道化役はザンニと呼ばれる喜劇的な従僕役であった。 (6)
伝統的にザンニは、最後には筋書きに戻る条件で、その間は、コースから離れ劇の大筋を演じることを許された.
ザンニの代わりに登場したのが、アレッキーノの役であった。イタリアの役の中では、最も人気があったものとされた。
彼は、まだらのつぎはぎの衣装を着て手には棍棒を持ち、剃った頭には、動物のしっぽ、または羽毛のたばのついた
帽子を被り、顔には黒い仮面をつけていた。
このアレッキーノがフランスに於いてはアルルカンと呼ばれていた。
アルルカンは、独白が巧みで、マイムが上手であり、即興、喜劇的いたずらや無鉄砲な動作を行っていた点である。
アルルカンが道化役から、次第に優位な役を演じるようになり、別の愚かな従者が必要とされ、ピエロが作られた
とされる。ピエロはフランスのナィーブな農民の出身とされ、田舎言葉を使用し愚かで間抜けだった。
しかしこのピエロも演じる役者によって変化した。
そして愚かで不恰好であり、ドタバタの道化役から、自己抑制をし情念を言葉も表情も殆ど無くて、全てを表現し、
嘲笑する役へと変化した。また哀愁と謎を取り入れた。衣装は、細かな変化はあったが、白い服と白い帽子、
白塗りの顔は、一貫していた。フランスに於いてピエロという役を不朽のものにした功績は、なんと言っても
「悲しきピエロ」ジャン・バティスト・ドゥビュローに帰する。(映画「天井桟敷の人々」に登場する道化師) (7)
 |
悲しきピエロ
ジャン・バティスト・ドウビュロー
|
イギリスのハーレクィーン(アルルカンの英語名称)は、18世紀のイギリスの舞台で活躍した道化役であった。
彼は、パントマイム(ここでは喜劇的な話の織り込まれた一種の演芸)の主人公であった。
19世紀には、ハーレクィーン従者であったクラウンが、ジョー・グリマルディーという役者によって有名になった。 (8)
それまでは、妙なまだら衣装で顔を赤く塗っていたが、彼により、白塗りで、眉、頬、口に朱を塗り、
モヒカン狩りのようなヘアースタイル、原色の衣装を着用し、非都会人、異人をイメージさせた。
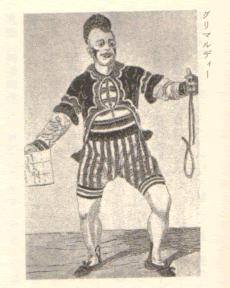 |
ク ラ ウ ン
ジョーグリマルディ
|
クラウンは、田舎のうすのろから始まり、ついには、おどけ者を指す敬語にまでなる。
クラウンが活躍する頃、同じイギリスで、サーカスが誕生した。このサーカスに登場し、曲馬のパロディを演ずる
芸人もクラウンと呼ばれた。サーカスクラウンは、グリマルディーのメークを取り入れ、次第に現在のメーク (9)
である太い眉、赤い鼻、大きな口へと変化させた。またイギリスのクラウンは、サーカスの世界にクラウン芸を
確立させ、19世紀後半には、一つのショージャンルとして確立された。
 |
有名なクラウンフラテリーニ兄弟 |
そしてサーカスのリングやミュージックホール、劇場、を活動の場所とし、サーカスの衰退と共にクラウンは、リング
を離れ、ミュージックホール、劇場、映画、テレビ等に登場し、その芸を見せるようになったとされる。
第4 日本に於けるピエロ・クラウン
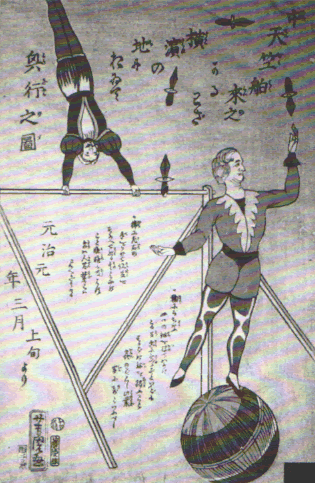 |
錦絵「中天竺船来之軽業」 |
現在、日本に於いて、一般的に道化師と称されているものは、ピエロである。このピエロの性格は主に2つに大別で
きる。
一つは、神秘的で悲しみのイメージを持つもの、もう一つは、底抜けに陽気で元気なイメージを持つものである。
後者の道化師は、日本では、ピエロと呼ばれることが多いが、実際世界では、クラウンという役名で呼ばれている。
では何故、日本では、クラウンという名ではなくピエロと呼ばれてきたのかを検証してみたい。
19世紀フランス文学の中での「悲劇的ピエロ」は、日本の詩人達が、フランス文学を翻訳することによって
日本に登場した。それは、明治の終り頃から大正初めにかけてである。大正時代には、既に、ピエロの白塗り顔と
衣装、悲しみの涙というのは日本に伝わっていたようである。当時の詩の中では、悲しき道化、かわいそうな者として
取り上げられている。当時の見世物に対する哀れという偏見が、曲芸は、寂しいものとされ、道化役のピエロは、
かわいそうな者、いとおしいものというイメージを生み出したものと思われる。
一方、明治初期、外国のサーカスも日本巡業にくるようになった。この外国での道化の滑稽ぶり、クラウン芸に
日本人は、強く興味を持った反面、この芸は日本人の気質になじめなかったようである。
その結果、明治にサーカスを移植したとき、このクラウン及びクラウン芸を排除した内容となった。日本のサーカスは
クラウンに代わり、曲芸もできない哀れなピエロが口上を言う役を務めるようになったとされる。
このサーカスのピエロは観客の目に哀れに映るよう、そして観客の同情の視線の中で存在していたようだ。
その後ピエロは、サーカスの芸人と混同され、芸人達への偏見のイメージを持つようになった。
そして一般大衆がピエロという言葉を使用するようになった昭和初期には、サーカスの道化としてのピエロが
定着していた。また初期には、ピエロはコメディアンの意味を持ったり、哀れな喜劇的人物であったりダンディとして
の意味を持つなど、様々な意味として使用されるようになった。
日本においてピエロは元来の意味を変え、想像以上に幅広い意味を持つようになったとされている。
参照文献
1) 道化と笏杖 ウィリアム・ウィルフォード 高山宏(訳) 晶文社 1983
2) 道 化 イーニッド・ウェールズフォード 内藤健二(訳) 晶文社 1979
3) 道化の社会史 S・ビリントン 石井美樹子(訳)平凡社 1986
4) 芸能の人類学 姫 野 翠 春秋社 1989
5) 演劇の歴史 フィルス・ハートノル 白川宣力(訳) 朝日出版社 1981
石川敏男
6)ある女子大生の卒業論文 この方の論文に負う所が非常に大きい。(名前不詳)
東京マッド 2002年2月6日 記
△トップ
|

